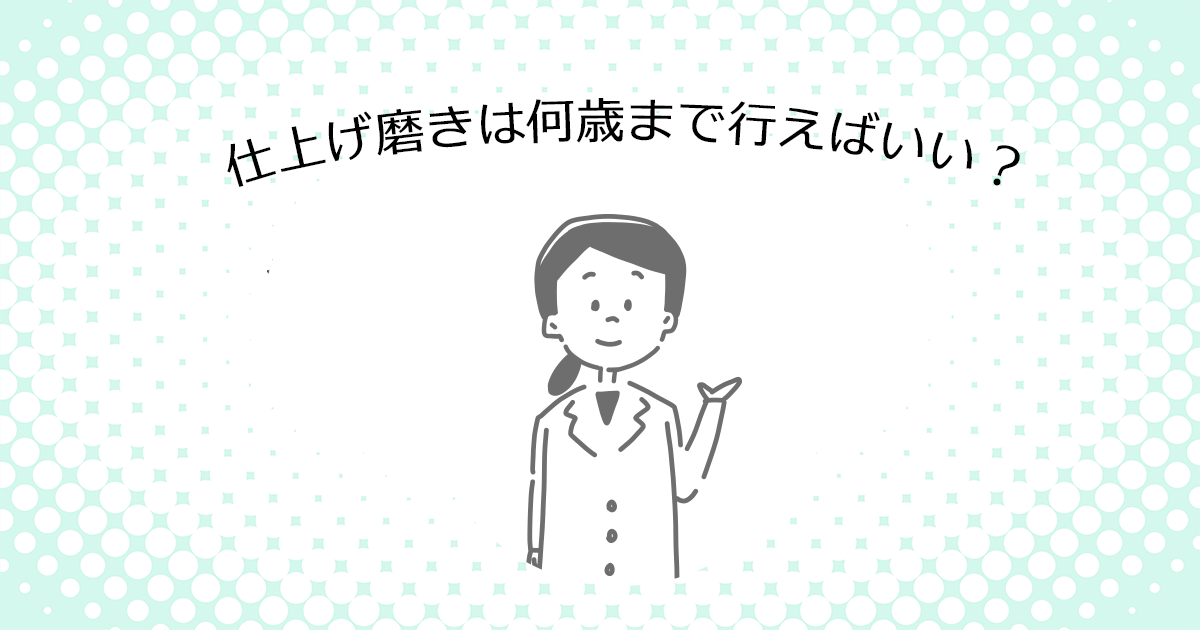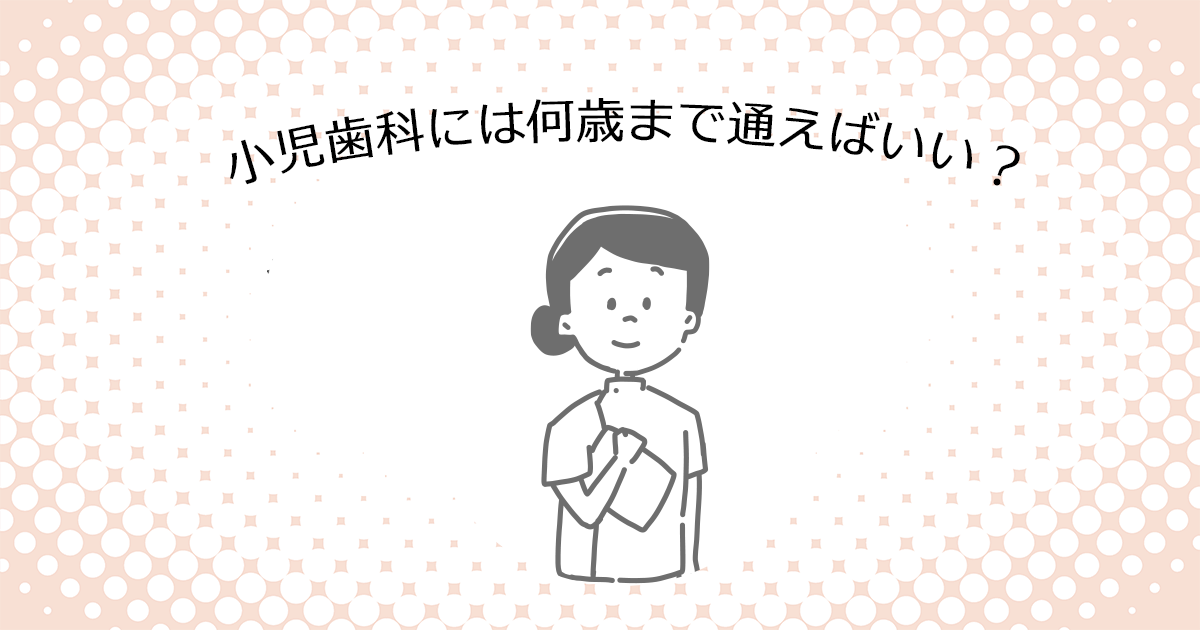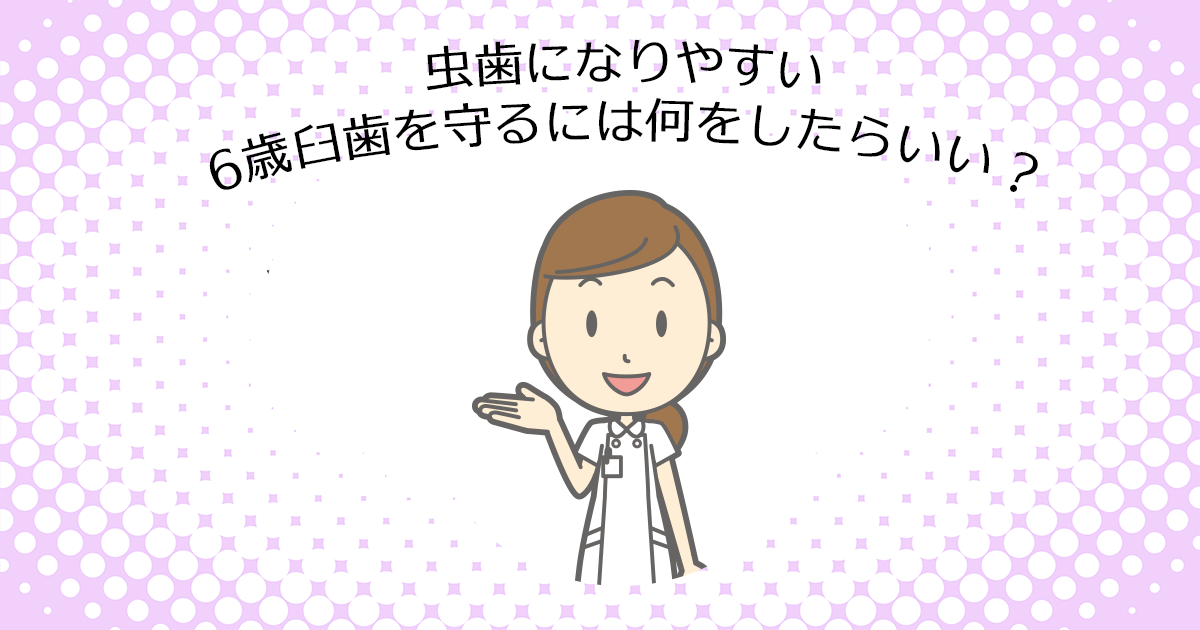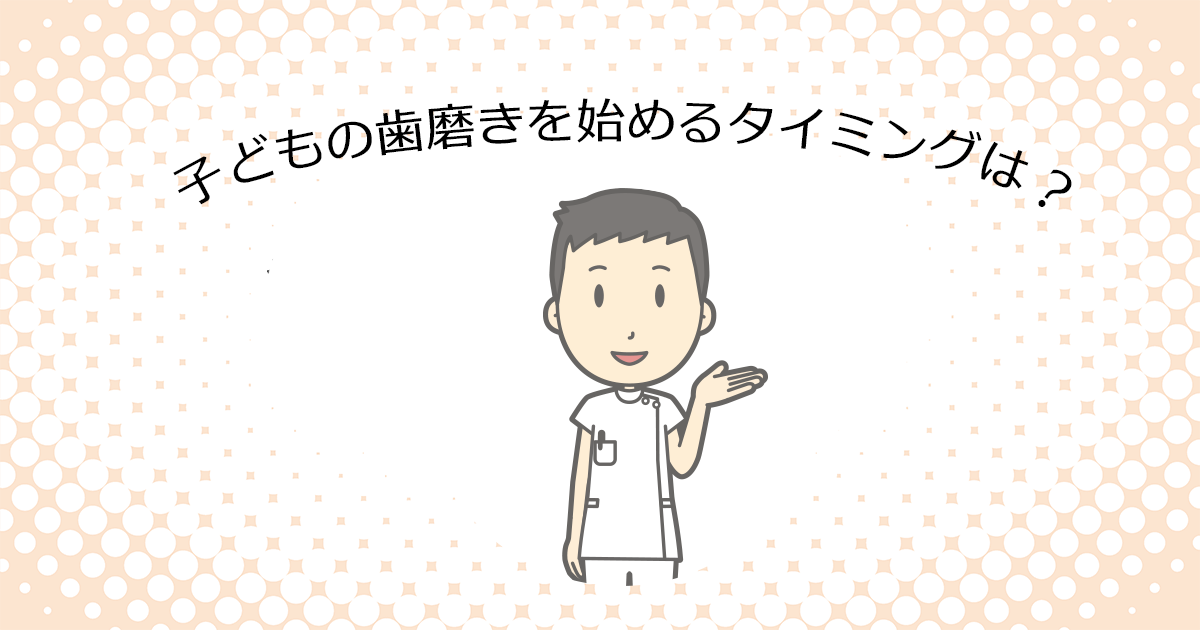子どもが小さいうちは、歯を磨いた後に保護者が仕上げ磨きをします。
しかし、子どもが小学生になると、「仕上げ磨きは必要なのか」と気になる保護者もいるでしょう。
仕上げ磨きは、何歳まで行えばいいのでしょうか?
また、仕上げ磨きを行うことにより、虫歯のない状態を維持するメリットとは何でしょうか?
仕上げ磨きは何歳まで行う?
歯が生えたばかりの頃は、子どもは自分で歯を磨くことができません。
そのため、大人が子どもの歯を磨く必要があります。
3歳頃になると、子どもが自分で歯を磨けるように練習を始めますが、最初のうちは十分に磨くことができません。
食べかすなどが残っている時間が長くなればなるほど、乳歯や生えたての永久歯は虫歯になってしまいます。
虫歯になるのを防ぐため、保護者が仕上げ磨きをして、子どもが歯磨きで落としきれなかった歯の汚れをしっかりと落とす必要があります。
子どもがある程度大きくなると、自分で歯磨きができるようになってくるため、いつまで仕上げ磨きをする必要があるのか気になる保護者も多いはずです。
仕上げ磨きは、何歳まで行うのでしょうか?
個人差がありますが、仕上げ磨きは小学4年生~6年生くらいまで行うといいでしょう。
なぜなら、小学6年生前後で生えてくる第2大臼歯には細かい溝があり、プラークが溜まりやすく磨きにくいからです。
第2大臼歯を虫歯にしないために、第1大臼歯などと高さが揃うまでは仕上げ磨きを行ってください。
子どもが仕上げ磨きを嫌がるようであれば、小児歯科を受診するのがおすすめです。
小児歯科では「染め出し液」などを使い、磨き残しを赤く染めて子どもに見せます。
視覚に訴えることで、普段の歯磨きでいかに磨き残しが多いのかを子どもに自覚させる効果が期待できます。
歯がしっかり磨けていないことを自分で確認できれば、子どもは仕上げ磨きの重要性を理解するでしょう。
ブラッシング指導も受けると、子どもは歯磨きのポイントを理解でき、歯磨きに対する意識が高まります。
しっかりと歯磨きをするよう習慣づけられるため、大人になっても清潔な口内環境を維持できるでしょう。
虫歯のない状態を維持するメリット
虫歯のない状態を維持していると、年を重ねても多くの歯が残りやすくなります。
健康な歯が多く残れば、食べることが楽しくなり、大きな口を開けた時に劣等感を感じることもありません。
乳歯が虫歯になると、その後に生えてくる永久歯にも悪影響があります。
したがって、「どうせ生え変わるから」と乳歯の虫歯を軽視するわけにはいきません。
虫歯菌が神経までたどり着くと、永久歯も虫歯になってしまいます。
子どものころから歯磨きをしっかりと行って虫歯のない状態を維持しましょう。
まとめ
子どもが小学生になると、今まで行っていた仕上げ磨きを嫌がるようになるかもしれません。
中には「自分で磨けるので、大丈夫」と言い出す子どももいるでしょう。
しかし、大抵の場合、自分では磨けたと思っていても、磨き残しがあります。
小学4年生~6年生まで仕上げ磨きを継続して行うことで、小学6年生ごろに生えてくる第2大臼歯を虫歯から守ることが可能です。
嫌がる場合は小児歯科を受診し、自分の磨き方では磨き残しがあることを理解してもらってください。