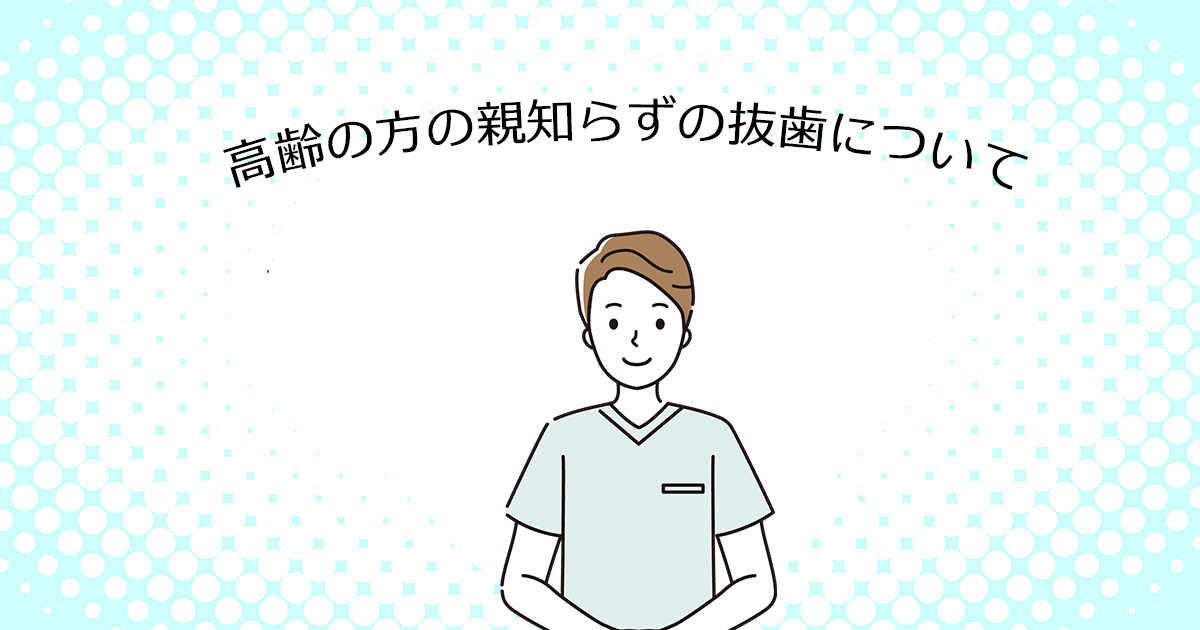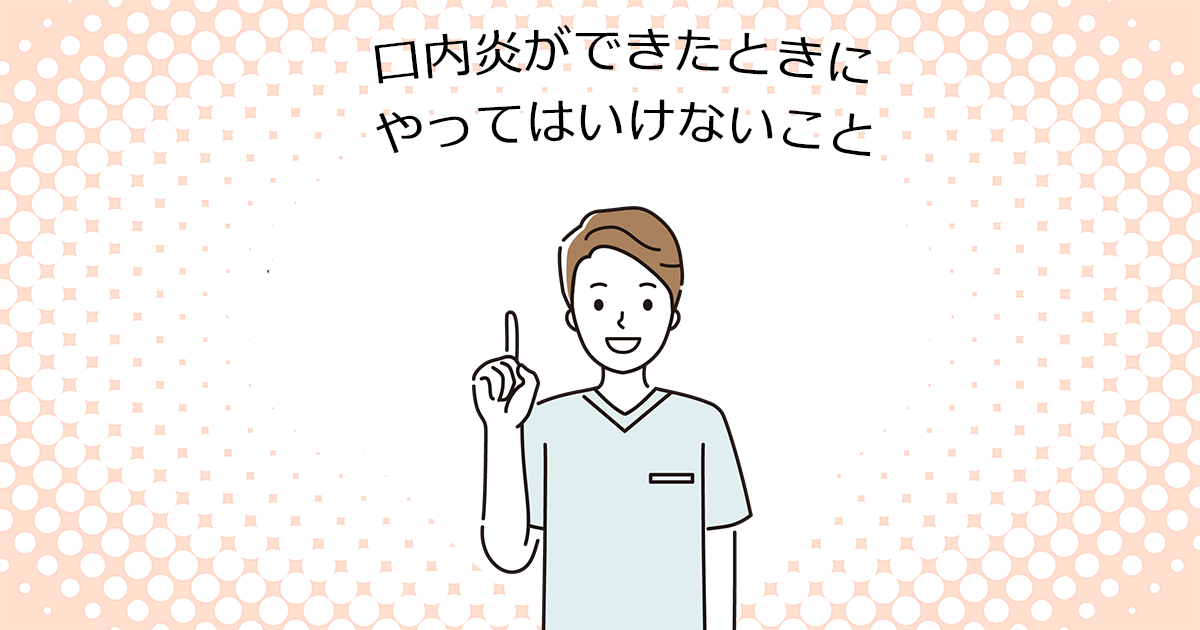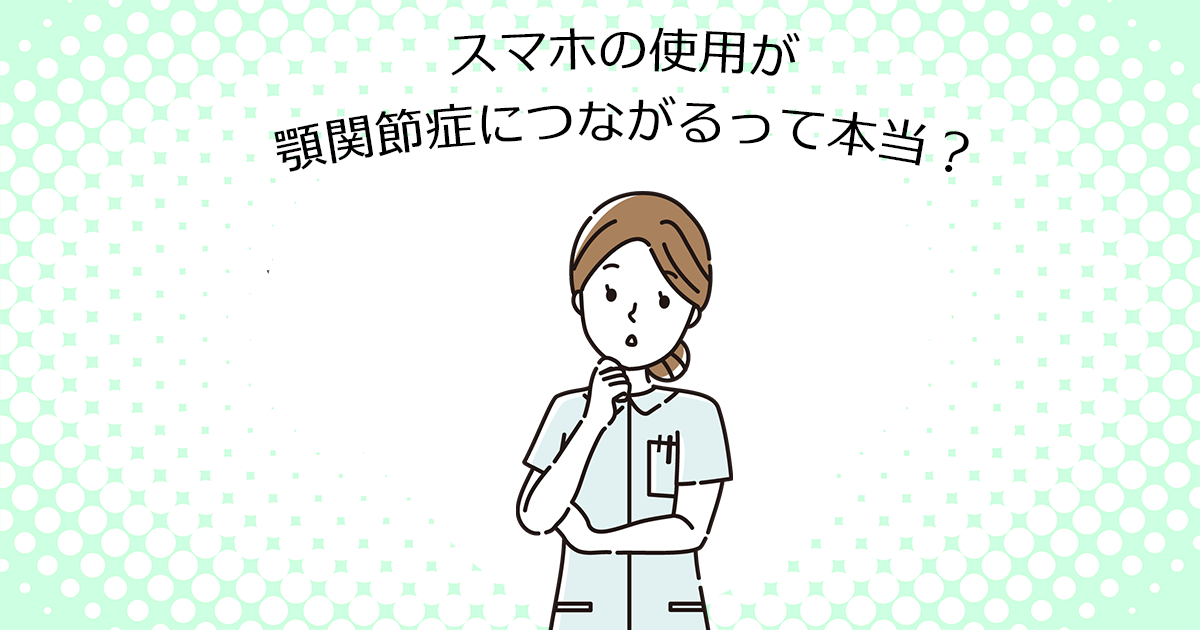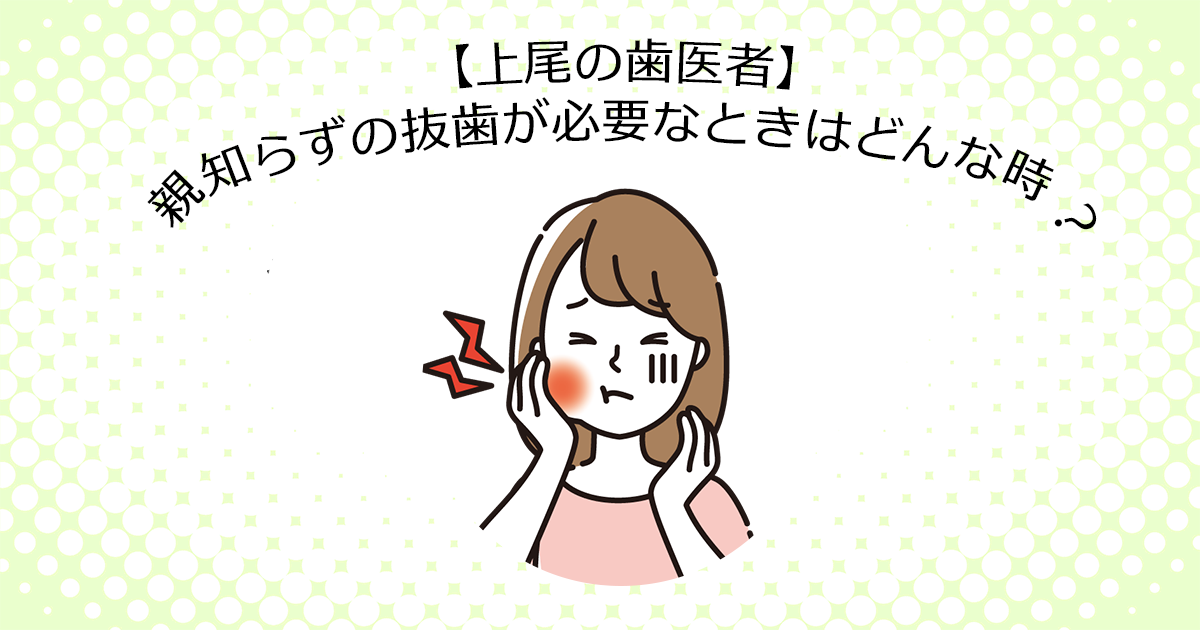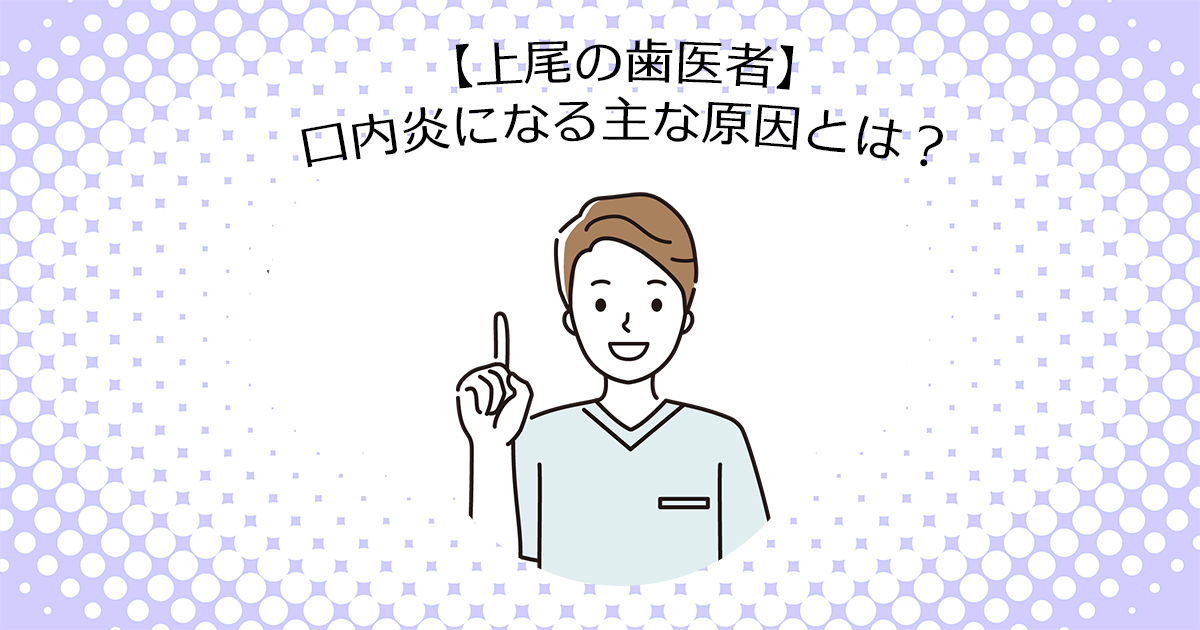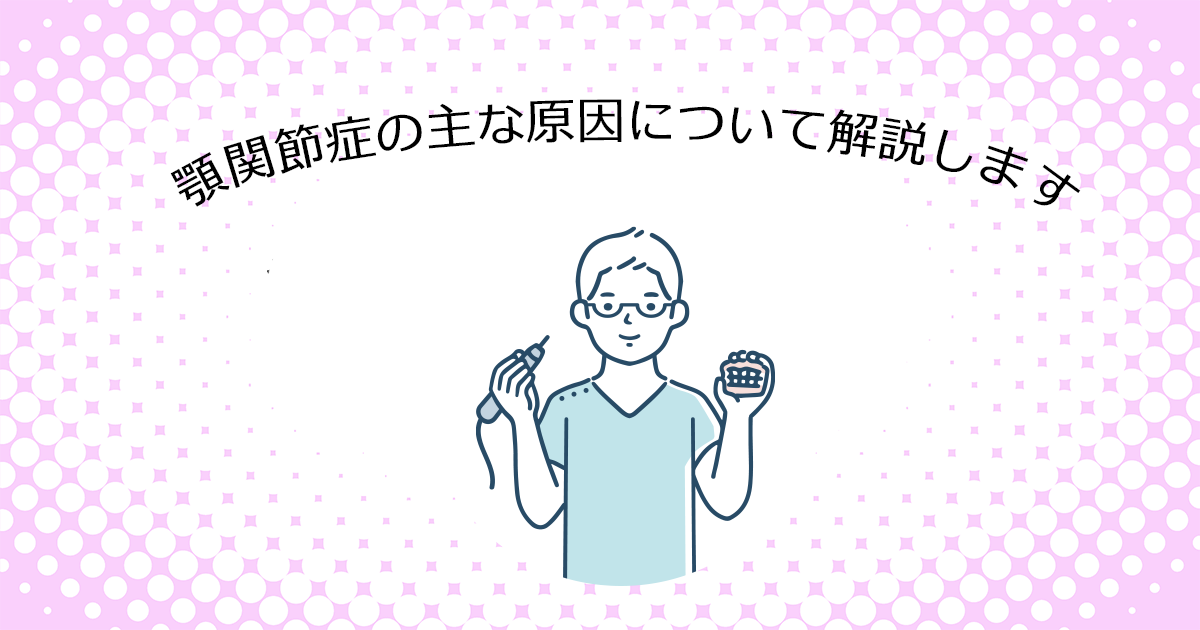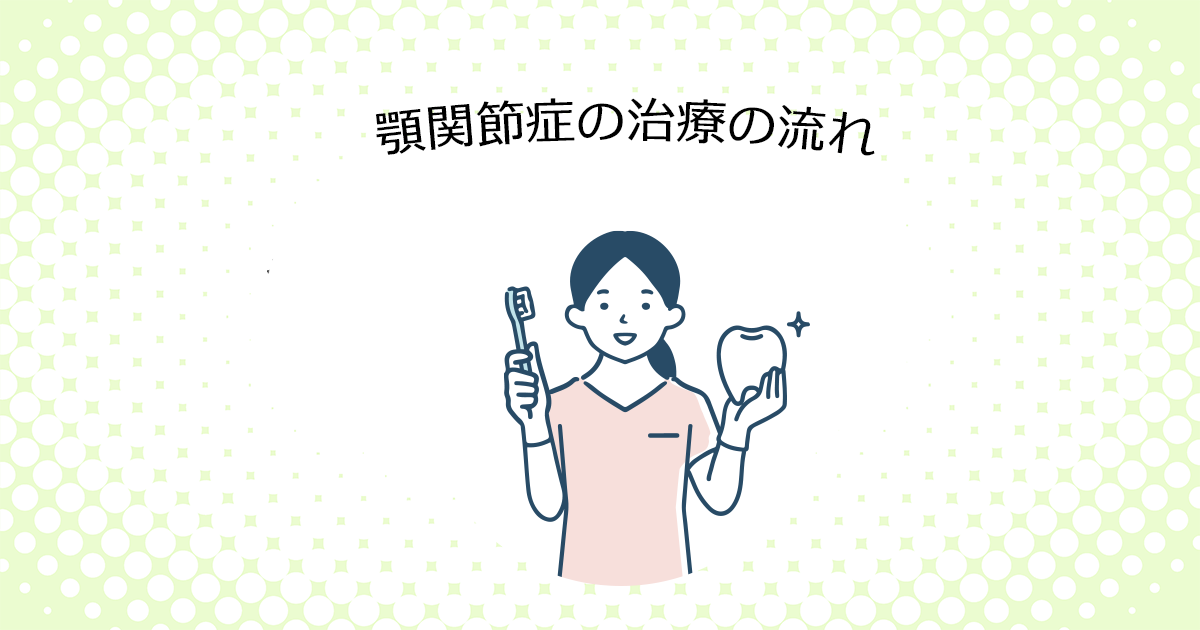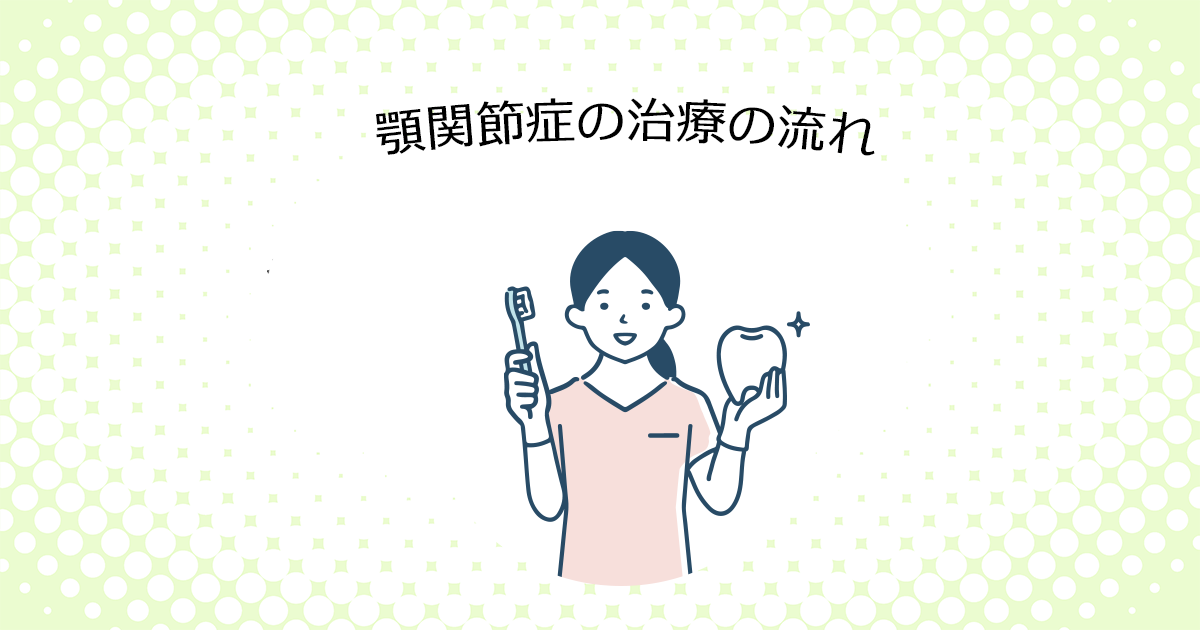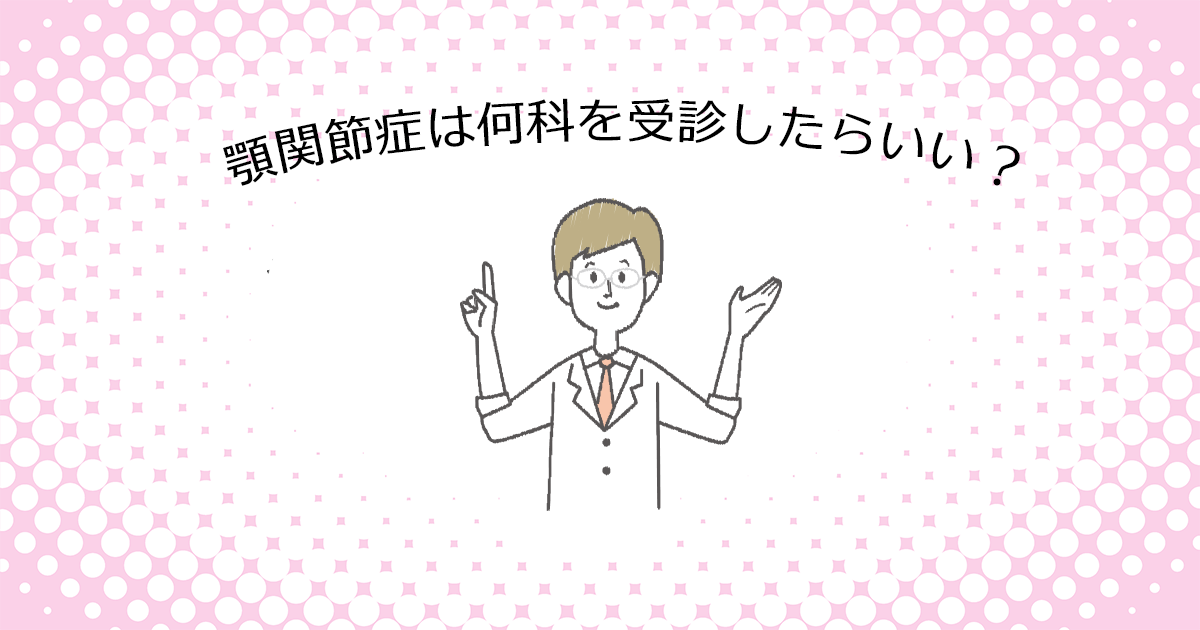親知らずが生えている方は、抜歯をするかどうか選択することになります。
このとき、隣り合う歯などに悪影響を与えている場合は、基本的に抜歯をしなければいけません。
また高齢の方でも、親知らずの処置が必要になるケースがあります。
今回は、高齢の方における親知らずの抜歯に関することを解説します。
高齢になって親知らずの存在に気付くケースがある
親知らずは、もっとも奥に生えてくる歯であり、前から数えると8番目の永久歯です。
親が知らない間に生えてくる永久歯であることから、こう呼ばれるようになったと言われています。
つまり親知らずは、通常思春期ぐらいから20歳くらいまでに生えるということです。
しかし、実際は萌出時期に個人差があり、30代もしくは40代で生えてくるというケースもあります。
また60歳以降など、高齢になって生えてくるケースは極めて稀ですが、高齢になって初めて親知らずがあることに気付くということは考えられます。
こちらは手前の歯が抜けたことにより、今まで隠れていた親知らずが見えるようになったというケースがほとんどです。
高齢の方における親知らずを抜歯するリスク
高齢の方は親知らずの状態にかかわらず、抜歯の難易度が高いとされています。
その理由は、疾患を患っていたり、体力面に不安があったりするからです。
高齢の方は高血圧症や糖尿病、骨粗しょう症などを患っているケースも多く、この場合は治療薬を服用します。
しかしこれらの治療薬には、出血量が増えるなど抜歯のリスクを高める作用があります。
また高齢になると親知らずと顎の骨が癒着してしまい、抜歯がしにくくなりますし、歯が脆い場合は抜歯時に割れてしまい、一部が歯茎に残ってしまうことも考えられます。
高齢の方の親知らず抜歯の判断について
高齢の方が親知らずを抜くかどうかは、基礎疾患の有無やリスクについて、歯科医師と十分に相談した上で判断します。
また少しでも腫れや痛みを軽減したいという方は、歯科口腔外科に精通した歯科クリニックを選ぶことをおすすめします。
ちなみに、高齢になる前からきちんと歯科クリニックの定期検診に通っていれば、手前の歯があっても親知らずの存在に気付ける可能性が高いです。
まとめ
親知らずがあるからといって、必ずしも抜歯をしなければいけないとは限りません。
しかし状態が悪い場合、たとえ高齢の方であっても抜歯をしなければいけないことがあります。
また高齢の方は抜歯のリスクが高いため、信頼と実績のある歯科クリニックを選ばなければいけません。
もっと言えば、抜歯の負担が少ない年齢で発見するのが望ましいです。